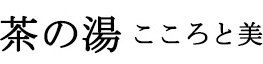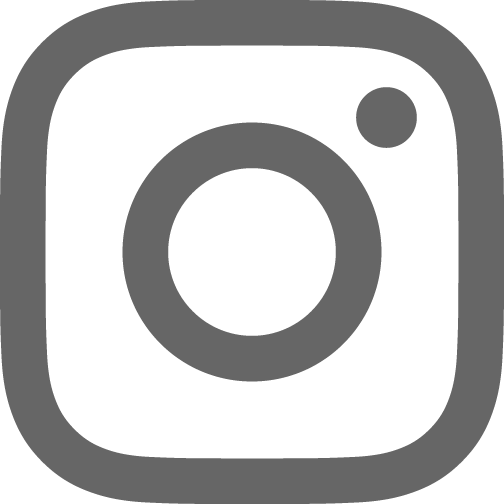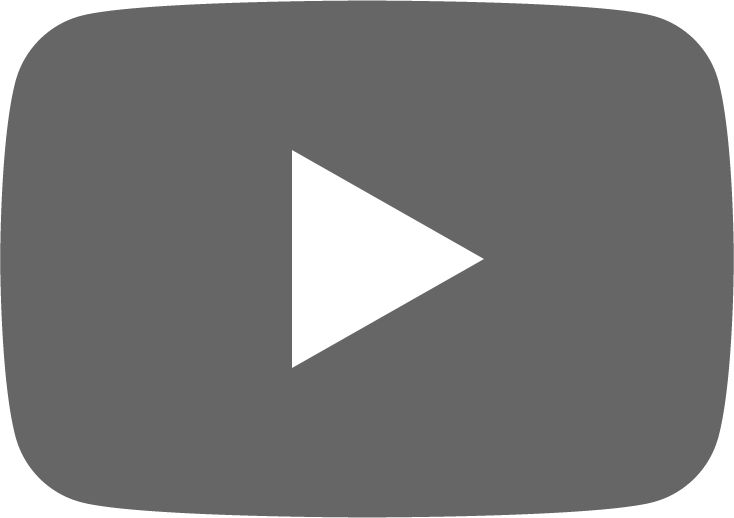表千家について
- HOME
- 表千家について
表千家の茶の湯の底流をなしているのは、千利休居士が大成した「わび茶」です。それは日本人の日常生活に深く根ざしており、人と人との心の交わりを大切にするものです。
また、その美は直接目に見える美しさではなく、茶の湯の風情のなかに美的な境地や心の充足を求めようとする精神をもって見ることのできる美しさ、すなわち目ではなく心で見る美しさであるといえます。
表千家には、一般財団法人不審菴と一般社団法人表千家同門会のふたつの法人があります。「家元の機構」と「社中の会組織」である2つの法人が両輪となって、表千家にふさわしい茶の湯のあゆみをかさねていくことができればと願っております。
表千家歴代家元

初代
利休宗易
<1522~1591>
安土桃山時代の茶人。茶道の家元三千家の初祖。幼名は与四郎、法諱は宗易。田中(千)与兵衛の子として堺に生まれる。武野紹鷗に茶の湯を学び、織田信長、豊臣秀吉の茶堂をつとめた。また珠光を深く慕い、珠光と紹鷗の茶を受け継ぎ、わび茶を大成した。
二代
少庵宗淳
<1546~1614>
千利休の後妻宗恩の連れ子。利休の自刃後、会津の蒲生氏郷のもとに預けられていたと伝えられる。徳川家康と蒲生氏郷の取りなしにより、豊臣秀吉から京都にもどることを許され、息子の宗旦とともに千家を再興した。
三代
元伯宗旦
<1578~1658>
清貧に甘んじて利休のわび茶の継承につとめる一方、息子たちを茶堂として大名家に仕官させるために奔走した。宗旦が息子たちに宛てた200通をこえる書状が「元伯宗旦文書」として伝来している。大名、公家、僧侶、町衆などと幅広い交流があった。
四代
江岑宗左
<1613~1672>
元伯宗旦の三男に生まれ、千家の家督と茶室「不審菴」を継承して、表千家の基礎を固めた。江岑から表千家の家元は代々「宗左」を名のるようになる。紀州徳川家に茶堂として出仕し、また聞書・覚書、茶会記、道具書付帳など多くの茶書を残した。
五代
随流斎
<1650~1691>
久田宗利と元伯宗旦の娘くれとの間に生まれ、四代江岑宗左の養子となって家元を継承した。家元の名である「宗左」に随流斎は「宗佐」の字を用いている。『随流斎延紙ノ書』をはじめ『寛文八年本』『寛文十年本』などの茶書を残した。
六代
覚々斎
<1678~1730>
久田宗全の子で、五代随流斎の養子となって家元を継承。号は原叟、流芳軒。覚々斎が仕えた紀州徳川家五代の頼方は、徳川八代将軍吉宗となり、吉宗から唐津の茶碗を拝領した。3人の男子に如心斎(表千家七代)、竺叟宗乾(裏千家七代)、一燈宗室(裏千家八代)がいる。
七代
如心斎
<1705~1751>
六代覚々斎の長男に生まれる。家元制度の基礎を築き、七事式を制定するなど、茶道人口増大の時代に応じた茶の湯を模索した。千家茶道中興の祖ともいわれ、利休を祀る祖堂(利休堂)を建て、利休以来の千家の道具や記録類を整理したことでも知られる。
八代
啐啄󠄁斎
<1744~1808>
如心斎の長男に生まれ、8歳で家元を継承した。天明8年(1788)の大火で焼失した家元の再建に尽力し、翌寛政元年(1789)には利休200年忌の茶事をおこなっている。60歳で隠居してからは宗旦を名のり、以後、「宗旦」は歴代家元の隠居名となった。
九代
了々斎
<1775~1825>
久田宗溪の子で、啐啄斎の養子となって家元を継承した。「数寄の殿様」と称された紀州徳川家10代治宝の家元への御成りを迎え、その後、治宝より武家門(現在の表千家の表門)を拝領した。今日にみる茶事、点前のかたちをおおよそととのえた。
十代
吸江斎
<1818~1860>
久田宗也(皓々斎)の子で、了々斎なきあと、幼くして表千家に養子に入り、家元を継承した。茶堂として仕えた紀州徳川家10代の治宝は茶の湯に熱心で、了々斎から一時預かっていた皆伝を吸江斎に授けている。天保10年(1839)には利休250年忌を迎えた。
十一代
碌々斎
<1837~1910>
十代吸江斎の長男。幕末維新期の茶道衰退期にあって、その復興に尽力。長崎、山口、広島など各地に出向いて茶の湯を広め、地方の工芸も茶の湯にとり入れた。明治13年(1880)に北野天満宮で献茶をおこない、同20年には三井家の主催により明治天皇に茶を献じている。
十ニ代
惺斎
<1863~1937>
明治維新後の茶道衰退の時代にあって、碌々斎とともにその復興につとめ、大正期の隆盛へと導いた。明治39年(1906)の火災により焼失した茶室の再建にも尽力。大正10年(1921)には家元内に新たな稽古場として松風楼を増築し、近現代における表千家茶道の礎を築いた。
十三代
即中斎
<1901~1979>
十二代惺斎の次男に生まれる。兄不言斎の逝去により、昭和13年(1938)に家元を襲名。第二次世界大戦の最中、昭和17年(1942)に千家同門会を発足し、昭和24年(1949)には財団法人不審菴を設立。現代における茶の湯普及と伝統の保持という組織機構の基礎を築いた。
十四代
而妙斎
<1938~>
十三代即中斎の長男で、昭和42年(1967)に大徳寺の方谷浩明老師より「而妙斎」の号を与えられて宗員となる。昭和54年に即中斎が逝去し、翌55年2月28日に十四代宗左を襲名した。平成2年(1990)には利休400年忌を迎え、法要をいとなみ茶事を催している。平成30年2月28日、代を譲り、隠居名の宗旦を名乗る。
十五代当代
猶有斎
<1970~>
十四代而妙斎の長男で、平成10年(1998)に大徳寺の福富雪底老師より「猶有斎」の号を授けられ、宗員となる。平成30年2月28日、十五代宗左を襲名。芸術学博士。不審菴文庫名誉文庫長として、家元に伝わる茶書の研究、出版を主幹する。主著、『近世前期における茶の湯の研究ー表千家を中心としてー』(河原書店)。