|
|
 |
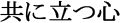 |
|
 |
かつて私は雪国に遊んだ時、日の降り注ぐ雪に蔽われた静かな山里を歩きながら、思わずはっと立ち止まりました。硬い凍土を割って青いふきのとうが、顔を出していたからです。その力強さと匂いたつ生気に圧倒されました。利休の言う「雪間の草」を目のあたりにして、これこそ茶の湯の境地なのだと感得したのでした。
利休は、茶の湯に使うすべての道具、点前や所作、主客の心の持ち方など、茶の湯のすべてを通じて、日本人の心を伝えようとしました。それは他を思い、共に立つ謙虚な心の持ち方です。お互い譲ることによって、そこから「和」が生まれ、さらには自然との「共生」にもつながります。
利休が長次郎に焼かせた茶碗の表情は、なんと静かで穏やかなことでしょう。けれども心をとらえ、何者も侵しがたい生命力を秘めています。
利休はこうした茶の湯を世にひろげるために、権力の中枢にまで入りこみました。秀吉をも簡素な侘茶に誘いこみました。しかし秀吉はきらびやかな黄金の茶室をつくって天下人の権力を誇示したのです。 |
 |
|
 |
即中斎手造黒茶碗 雪間草
 |
|
|
|