|
|

|
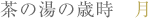
|

 |
 |
 |
 |
啐啄斎 宝暦12年(1752) 9月27日の会記より
汁は鱧と菜、平椀には鯛のくずあんが供された。 |
|
茶人は「粗茶一服」、つまり茶事にて客をもてなす際には栗・柿・松茸等山の物。秋刀魚(さんま)・鯖・鱧といった海の食材を用いた料理でお迎えする。向付は昆布締めの鯖。汁は南瓜を具に赤出汁(あかだし)で。お椀には鱧の葛たたきに菜の物、アクセントとして松茸を添えるのもいいでしょうか。或いは、蓮根を磨り潰した蓮饅頭を椀種に用いても良いかもしれません。炊き合わせは里芋など山の物の炊き合わせ、和え物(あえもの)にはホウレン草に焼いた松茸の細切りと菊を和えた物。八寸には焼栗などは如何でしょうか。
私共茶人が振る舞う懐石はあくまでもお茶の妨げに為らないものが理想です。四季の忘れられつつある飽食の時代、家族団欒で頂く料理の様な献立でも構いません。丁寧に調理し、季節を楽しむために客を迎える。そこが一番大切ではないでしょうか。
|
| |
|