|
|

|
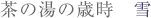
|

 |
 |
 |
 |
覚々斎 享保11年(1726) 正月5日の会記より
重箱で鰤の焼き物が供された。 |
|
北風が吹き雪が降り積もる中、未だほっこりした根菜類の炊き合わせが美味しく感じる時期です。根菜類を用いての沢煮碗(さわにわん)を懐石に取り入れてはいかがでしょうか。人参・大根・三つ葉等を針千本にして湯通しをした後、鶏のささ身を少々と胡椒であっさり仕上げます。焼物は旬の脂ののった鰤。こちらも塩だけとシンプルに焼き上げる。旬の食材だからこその味わいです。向付は甘えび。殻を剥き尾っぽは残します。わさび醤油で頂くと優しい甘さが際立ちます。また折角ですから瑠璃色に輝く子を塩水にて洗い、一日ねかせて肴として燗のあてに出すのはいかがでしょうか。半世紀前までは漁師も捨てていたそうですが、ある茶人が考案し、自身の行く先々で教えて廻ったという品でもあるようです。また炊き合わせの代わりに、白子に片栗をまぶし油でサッと上げる。それに紅葉おろしと浅葱を添え、出汁をかけ頂くのも良いかもしれません。八寸には、ほろ苦い蕗の薹を炊いたものを山の物に。海の物には白魚を5匹ほど、薄いあて塩に5分くらい漬け、それを布巾に取り、焙ったものに雲丹や黄身をぬったものを頂きたいものです。
春に向かい生命の息吹を感じる食材にてもてなすのも、季節の移り行く楽しみ方の一つかもしれません。
|
| |
|