|
|

|
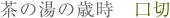
|
 |
|
|
 |
|
「鶴宿千年松」
|
|
 |
梢を渡る秋風は一層冷気を帯び、山の紅は鮮明となります。近隣の社寺の境内に通ずる参道も庭との境もなく紅の絨毯を敷き詰める頃、冬の足音が急ぎ足でやってまいります。利休の頃は柚子の色付く頃、元伯の頃は吐く息が白くなる頃と申しておりました開炉。「陰陽五行説」の渡来と共に宮中では亥の月亥の日が水の季節の始まりにあたりその日より炉に火が入りました。民間では『亥』の子沢山にあやかり子孫繁栄を願い、餅を配った風習と重なり茶人達は立冬の前後の亥の日に開炉を行い亥子餅を頂く様になりました。初夏に近づく八十八夜を前後とし、採れた新茶の若葉を摘みとって一袋(たい)半袋(たい)と種類と量を分けます。出入りの茶師に秘蔵の茶壺に詰めさせ、半年ねかせた壺の封の口を切りその年の茶を楽しむ。「口切りの茶事」或いは壁を塗り替えた炉を開いて釜を掛ける「開炉の茶事」と新茶を愛でる季節の到来です。
|
|