|
|

|
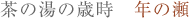
|
 |
この事始めを過ぎますと、床に「先今年無事 芽出度千秋楽」の掛物が掛けられ、稽古仕舞いを行う方が増えてまいります。町中では空也上人の故事にちなみ半人半僧の鉢叩き姿の茶筌売りを見かけるようになり、いよいよ新年に向かっての準備が本格的に始まります。大掃除や歳徳棚(としとくだな)を設置と気が付けば大晦日。大晦日には除夜釜を掛けられる方も多いと思います。
家元におきましては年末の火が着実に翌年に受け継がれますようにと、残月亭の炉中に埋(うず)み火がなされます。大切な火守りの儀式です。
さて、この忙しさと極寒の中で春までの楽しみは、夜咄の茶事。柚子等をふんだんに用いた懐石でお客様と共に一時(ひととき)からだの芯までほっこりしたり、詩人たちの詩・たとえば高適(こうせき)の「除夜」や、陶淵明(とう えんめい)の「帰鳥」等に思いをかさね、新年を迎えたいものです。
|
 |
|
|
 |
|
「啐啄斎筆 鉢叩き画賛」
|
|
|