|
|
 |
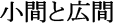 |
 |
お茶とお香と、これら二つの芸道文化は、まったく同じ社会環境の中でそれぞれの歴史的な歩みを続けてきました。東山文化に産声を上げたこと。寄合いを旨とすること。禅文化の影響を濃く受けていること。季節の移ろいにとても敏感なこと。共通項はいくつも見出せます。
しかし、東山文化の時代からおおよそ百年、利休によって侘び茶の大成がなされた頃には、それぞれがかなり違った世界へ歩みを進めていたようです。草庵の小間に究極の緊張感を求めた茶の湯に比して、聞香は、常に広間を好みました。希少な天然の香木に対する価値感から、人々は、小片の香木を火にかけて消費するときにある程度の人数を求めたのだと思います。江戸期に入ると、香道具のデザインは十人を基本に整えられるようになりました。
十六世紀初頭、まだ戦火の跡から復興できない京都を余所に、堺は都市国家として繁栄します。琉球貿易の担い手として、会合衆達は大層な活躍を続けました。その取り扱い品として舶載された数多くの珍器が、茶の湯の発展に大きな礎となりました。この貿易によって沈香木も輸入されていたようですが、いかにしても香木は消耗してしまいます。
またこの時代、寄合いのいまひとつの手立てとして連歌も親しまれました。和歌の上句と下句を詠い継ぐ歌合せの形態に工夫を得て、香りで情緒を楽しむ聞香にも「たき合わせ」という方式が生まれました。参会者が持ち寄った銘香木を幾種も焚いて楽しむとき、その香銘を継ぐことによって連歌と同じ寄合いの楽しさを見出したのです。これらのことから、聞香の機会には広間において一定の人数で時空を共有する必要が、自ずとあったのです。
| |
|
|
|