|
|
 |
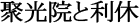 |
 |
弘治年間(1555~1558)は京都を脅かすような義輝、晴元も軍行動もなくなったので、この折に、長慶は新たに父元長の菩提を営むため、堺の舳松(へのまつ)町にあった大徳寺の子院である南宗庵を宿院の南に移転し、自らが深く帰依し参禅する大林宗套が開基となり、新たに名を南宗寺として建立しました。
これが現在堺の南宗寺であります。
南宗寺を支援してきた堺の商人が度々参禅し茶会を開いており三好家だけでなく、茶道の千家塔所もあり堺の都市民に開かれた寺院でもありました。
利休は10代で北向道陳、武野紹鴎に入門して以来70歳で没するまで、長い年月茶道に関わって来た、三好家の寺というよりは、利休の寺との方が世間周知となっております。
利休以来の千家とも縁の深い寺であり、利休と最も深い有縁の大徳寺僧、古渓宗陳(1532~1597)と春屋宗園(1529~1611)を育てた笑嶺宗 は、はじめ古嶽宗亘に参じていましたが堺の南宗庵に住していた大林宗套の印可を受けます。 は、はじめ古嶽宗亘に参じていましたが堺の南宗庵に住していた大林宗套の印可を受けます。
天文22年に「笑嶺」の法号を授けられています。
|
 |
|

|
| 三好長慶画像
|
|
|
|