|
|

|
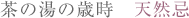
|

13日には中興の祖と言われる如心斎に敬意を表する為に、家元では天然忌が行われます。残月亭では「花寄せ」、九畳敷では「且坐(さざ)」。新席に於いては隔年に、「一二三」と「数茶」が行われます。如心斎は先に述べた七事式を参禅の師である大龍和尚や彭祖宗哲(ほうそそうてつ)、川上不白といった方々と制定。最晩年には「利休遺偈」を江戸・冬木家より戻された事もあげられます。他にも、利休150回忌に合わせ敷地内に祖堂を建立、利休以来の茶の湯の教えを整理、今日の家元制度を整えるなど、約20年の家元在位の間に多くの事を残されました。
江戸中期・文化繁栄の
元禄を超え生活水準が飛躍的向上をする中、文化面でも華やかで多様化する時代。現代と通ずる時代背景の中、温故知新を体現された方に感じます。
1日が巡る様に式も同じく巡ります。太陽が沈み夜の帳が降りる頃、東の空に天空の宮殿が昇れば、白居易(はっきょい)の「対琴待月(琴に対して月を待つ)」あるいは、武帝(ぶてい)の「秋風辞」の様に想いをはせ、秋の夜長の名月を楽しみたいものです。
|
| |
|