|
|
 |
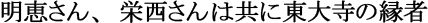 |

茶の世界に大きな足跡を印した明恵さん、栄西さんは共に東大寺と最もゆかりの深い方でした。
先年、私の師父澄園大僧正が遷化、その遺品の手文庫を整理しておりました。文庫底にひっそりと茶のハトロン紙封筒が収まっていました。表記なし、中に一片の紙。
早々に古文書博士の堀池春峰先生に読んでいただきました。
「上野さん、これは大変なものですよ。東大寺にはもっとあってしかるべきものなんですが、滅多とない、明恵さんの真筆メモです。貴重な資料です、お大事にしてください」とのことでした。なんの変てつもない紙片は、わが真言院の第一級の“寺宝”となったのです。
明恵(高弁、1173~1232)は紀州の人で高雄の神護寺に入寺、文覚上人に師事、16才で東大寺で受戒、後鳥羽院から高雄の栂尾の地を拝領、栄西禅師から譲られた茶の樹を植え「栂の尾茶園」を拓かれました。
明恵さんの遺訓「阿留辺幾夜宇和(あるべきようわ)」で、僧は僧のあるべき様、俗は俗のあるべき様、と説かれています。利休居士の道歌「野の花は野にあるように」に相通じます。悟道に達した方は、どこかで一致されるのでしょう。 |
| |
|
|