|
|
 |
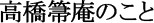 |

あまりに面白い本の虜になっているうち、下車するはずの夙川駅を乗り越し、三宮まで行ってしまったことがあります。問題の本は、熊倉功夫著『近代数寄者の茶の湯』(河原書店)でした。この本によって、箒庵(そうあん)高橋義雄という近代日本が生んだ偉大な数寄者がいたことを教えていただきました。
「数寄者の茶が既成の概念にとらわれない自由闊達な茶の湯であったということ、彼らは旧来の茶の破壊者であった」
熊倉功夫先生は、近代数寄者の革新性をこう記して、その精神的背景は近代合理主義にあったと書いています。しかし、数寄者の近代化は決して西洋化ではありませんでした。日本の伝統文化に深く根差したものであったことを喝破しています。
高橋箒庵は「時事新報」で福沢諭吉の薫陶を受け、若くして論説に健筆を揮ったジャーナリストでもありました。熊倉先生は、そのひとの横顔を活き活きと描きながら、「われわれの足元から、根こそぎ数寄の世界が消えつつある」と危機感をあらわにしています。
茶道史の泰斗がそういわれるのですから、危機は眼の前にあるのでしょう。だとすれば、私が而妙会で拝聴している北村美術館の木下收館長の一言ひとことは譬えようもなく貴重な光芒なのかもしれません。
|
| |
|
|