|
|
 |
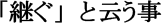 |

襲名は特に大げさな事なきよう、ただ、茶事を粛々と続けて参りました。できるだけ略することなく正式な正午の茶事、当代と隠居の二人三脚、小間での懐石は二人でもてなし、濃茶は私が、薄茶は広間に移り当代吉左衞門が致します。
樂家の小間は三畳本勝手下座床、露地からの入口は躙口ではなく3枚の小障子がはまっています。露地に向かって深い庇が延び、軒(のき)内に蹲いがあるという少し変わった造りを持っています。庵号は「麁閑亭(そかんてい)」、恐らく元禄年間にこの茶室が建てられた時に覚々斎宗匠から五代宗入が戴いた庵号、今ではすっかりやつれ、幽かに字を辿れるほどになお、軒下に揚がっています。
広間は「翫土軒(がんどけん)」、こちらの扁額は了入が了々斎宗匠から戴いたもの。七畳の間、実際には六畳で、残す一畳は床脇右に台目板がはまり、そこを一畳に数えます。啐啄斎宗匠好みの七畳の間を模したものです。樂家の七畳はそれでも少し変わりもので、広間なのに若干小間風侘好み、床柱は赤松の皮付き、なぐりの入ったアテ柱、しかも洞床となっています。
|
| |
|
|