|
|
 |
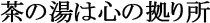 |

私が而妙会へお誘いを戴いたのは母が旅立って程なくしてからでした。
私はお茶について何も知らないばかりか、どの様にお茶に接したらいいのか答えが見つからず、不審菴のお稽古に伺うのは気後れがし、心許ないばかりでした。私は茶の湯の心とは何なのか知りたかったのです。
そんな時、而妙斎宗匠の『茶の湯随想』を読み、まさしく眼から鱗でした。どの頁を読んでも心に沁みる言葉ばかりで、而妙斎宗匠はお茶の心とは相手を思いやる心であり、心づかいであり、おいしいお茶を召し上がって頂くこと、と書かれています。
村田珠光の言葉「慢心する心や我執を持つことが茶の湯で一番悪いことである」を紹介され、武野紹鴎が利休居士に与えた侘びの文を引き「正直で慎み深くおごらないさまを侘びという」と説かれています。そして茶の湯の究極の目的は点前を含めた人格の形成にあり、茶の道は自得しながら「おのれの未熟を絶え間なく克服し学んでいくもの」と教えて下さっています。これこそが私の知りたかったことなのでした。茶の湯で大切なことは、人としての在り方そのものだということです。
私にとって、茶の湯とは何なのかという疑問が払拭され、茶の湯の本質が体の中にしっかり根付いた思いがいたしました。心許なさは吹き飛び、心の拠り所が出来たのです。お茶に向き合うのが楽しくなりました。
|
| |
|
|