|
|

|
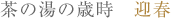
|

1月は、初釜の時期。御膳はお正月にちなんだ物はいかがでしょうか。
椀物をお雑煮にする。京都では濃い目の出汁に白味噌をとき御餅、そして人の頭になる様にと願って頭芋をいれます。お雑煮は地域によって多種あります。すまし汁に御餅と花かつおをのせる。カツオの香りが立ちあっさりしたのもいかがでしょうか。またそこに鴨肉・人参・水菜・柚子を入れることにより少し華やかにするのも良いかもしれません。向付はお目出度い鯛や、塩抜きした数の子をスライスし、一晩出汁に浸した物を出すのも正月の雰囲気を楽しむのには良いかもしれません。口取はご祝儀のものです。大根膾、柿膾、沖膾といったものをツボツボに入れてはいかがでしょうか。膾は利休の会記にも度々出てきております。ツボツボは伏見稲荷の神器・デンポウが起源とされ、元伯が好まれ家紋の由来にも繋がります。八寸は海のものとして伊勢海老の切り身に練り雲丹を、刷毛でぬり軽く炙った物や、赤い所を取り除き、共白髪願った白髪海老。山の物として柚餅子或いはチシャトウの西京漬けを。赤と青のコントラストが八寸盆に映えるのではないでしょうか。少し豪勢に預鉢として旬の越中梅を醤油とお酒で炊いて味をととのえたものを出すのもいかがでしょうか。雪降る寒い時期、暖をとるなかでの熱燗。一献頂く際の肴としていいかもしれません。
茶事は客をもてなし、お茶をより楽しんで頂く事ですが、その本質は相手を気遣う事にあります。お正月の御馳走で少し弱った身体を労り、人日の日に習い味付けを薄いものに。七草粥など胃に優しく味付けもシンプルなもの、食材本来の味を楽しむ事も、一興かもしれません。
|
| |
|