|
|

|
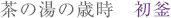
|

「初釜」、元は「稽古初め」とのこと。昭和に入り参上する方がふえ、然るべき日程でお招きする様になりました。
松風楼に於いて薄茶を先ず一服、次に残月亭で濃茶。床には元伯筆「春入千林處々鶯」が掛けられます。この掛物は、春秋対句の「春入千林処々花 秋沈万水家々月」を元伯が春の花と共に鶯の声に惹かれて書かれたと思われます。花入は青竹に曙椿・結び柳を生け、台子の諸飾(もろかざ)りで嶋台茶碗で濃茶を頂きます。嶋台は如心斎が好まれたのが最初とされ、塗物の盃を重ねたものを倣ったとされています。本歌は長入作で川上不白が江戸に旅立つ際送ったとされています。また吸江斎好み等、歴代の好みの嶋台があります。吸江斎好みは紀州家に初出仕の文政10(1827)年に樂旦入より納められ、治宝(はるとみ)侯にこの茶碗にてお茶を差し上げたとされています。濃茶の後は、新席にてお膳を頂きます。昔からお正月の吉例の際に用いられる鴨雑煮や、寒い折ですので温かい蒸し寿司をお出しし、召し上がって頂きます。
そういった降雪の折、「雪継渓橋断(ゆきは けいきょうのたたれるをつぐ)」や柳宗元(りゅうそうげん)の「江雪」の一句を用いた掛物で暖かな春の訪れを待ちたいものです。
|
| |
|