|
|

|
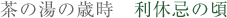
|

また、3月と言えば茶道に携わる者にとっては忘れてはならない利休忌。御家元では宗匠自ら御茶湯(おちゃとう)が行われます。菩提寺・聚光院様の拝経、七事式の茶カフキ・廻り花が行われます。それに習い、社中の各稽古場でも茶カフキを行ったりするところもある様です。古くは家元でも精進家具を用いて御供えした御膳と同じ物を振る舞っていたとのことです。
この利休様の畏敬の時期でもある春。床には利休も好んだ藤原家隆(ふじわらのいえたか)公の「花をのミ待つらむに人に山里の 雪間の草の春をみせばや」を始めとした歌の掛物を掛けたいものです。あるいは蘇軾(そしょく)の春夜や王安石(おうあんせき)の夜直(やちょく)などの一句を用いた掛物を掛け、桃の花弁を浮かべた桃花酒や白酒を用いたり、菱餅やあこやにて釜を掛け、未だ肌寒い春の夜空を眺め過ごしたいものです。
|
| |
|