|
|
 |
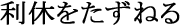 |
 |


茶を掬う茶杓は、はじめ中国から伝えられた薬匙などの匙が用いられ、材質も金属や象牙でした。
珠光、紹鴎のころから竹の茶杓も用いられるようになりますが、節なしや切留めといわれるように節止めにしたものでした。
利休は畳の目数にして13目ほどの竹の茶杓の中段に節をもってきました。茶を掬う節から上の部分、手に持つ節から下の部分の変化、節裏の削り具合、どれもが微妙に変化し、全体としてまとまって調和しています。
竹という自然の材を極限まで削りこみ、茶を掬うという用の中に自身の美意識を表現した利休の茶杓は見事という外はありません。
|
 |
|
|
|
|