|
|
 |
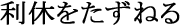 |
 |
|
 |


天正18年小田原より帰洛した利休は聚楽第の屋敷において茶会を催します。これら一連の茶会は「利休百会記」としてその様子を今に伝えています。
天正19年1月13日には秀吉を、そして翌月閏1月22日には徳川家康を招いて茶事を催していますが、百会記の記録はこの日を以って終わります。
この間大徳寺における山門利休像の問題が出来したのでしょう、閏1月21日には大徳寺に出向いています。
2月4日には、利休が大切に所持し自らの茶の歴史と共に歩んだといえる茶壷「橋立」を大徳寺聚光院に預け、「御渡しなさるまじく候」と伝えています。利休の身に迫った危機が窺えます。
そして終に2月13日秀吉の堺への追放令により、利休は夜に淀より舟にて堺へ下っています。
十三夜の月の中を。
思い遣れ都を出て今夜しも
淀のわたりの月の舟路を
|
|