 |
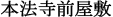

秀吉は京都に聚楽第を築き、ここを中心として京都の街の改造を始めます。堺より京に出た
少庵は、始め大徳寺前に住したとされますが、天正10年以後に二条衣棚に屋敷を構えます。
この地は日蓮宗妙覚寺のあったところですが、寺は天正11年に移転し、その後にここに
住んだものと思われます。
その地も釜座通が突抜けて新しい町割りとなるため、天正18年に替地として今の本法寺前の
土地を与えられたといわれます。
本法寺は日蓮宗の本山で、本阿弥一族の寺として知られ、住職は日通上人。上人は堺の油屋
一族の出身であり、利休の師北向道陳に縁のあった人と思われ、また画家長谷川等伯を指導
した人としても知られ従姉妹が等伯の妻になっています。
本法寺前に替地が決まったということについては、本法寺の口添えがあったという伝えが寺
にあるということですが、以後この地が千家代々の屋敷となるのです。
|
 |
|
|