|
|

|
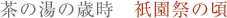
|
 |
|
|
 |
また7月と言えば、7日の七夕・星祭りが行われます。一般には笹の葉に願いを書いた短冊をかける行事です。本来は針仕事や機織りなどの技芸向上を願い行われる乞巧奠(きっこうてん)が元になります。現在でも鎌倉時代の歌人・藤原定家の流れをくむ冷泉家(れいぜいけ)において、毎年行われております。この乞巧奠では梶の葉に詩を書き和歌の上達を願い、一夜を明かし楽しむ行事になります。五色の糸を垂らした内側に祭壇を設け、盥に水を張り水鏡としたものを飾ったり、あるいは琴等の楽器を飾ったりします。この楽器を飾る事、技芸向上は勿論ですが、宮中に於いては唐楽や高麗楽の代用として飾ったのではないでしょうか。この乞巧奠の様子を詠ったのでしょうか。家元には吸江斎賛・狩野永岳筆の「梶まりの画」という掛物があります。歌人たちの楽しい一時を詠ったのでしょう。夜通し行われる雅な習い事を伝えるように感じます。
盛夏を迎え、日中の暑さがより強く感じるこの時期、范成大(はんせいだい)の「州宅堂前荷花」の涼感感じる詩、あるいは夜空を眺め李賀(りが)の「七夕(しちせき)」の想いを重ね、季節を味わう葛焼や鱧(はも)を用いて朝茶にてお客様を迎えたいものです。
|
|