|
|
 |
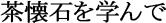 |

私が入門しましてすぐに、稽古茶事の懐石について、献立のことから丁寧に教えて頂きましたが、納得のゆく料理に到達するには随分時間がかかりました。一度、菅田宗匠の手造りの懐石をいただきましたが、これこそ真の茶人の懐石といたく感銘を受けました。
永樂即全先生から「菅田さんの手料理は、玄人が裸足で逃げんならんレベルやなぁ」と聞かされていたことを思い出しました。実践に続く実践で、到達された手料理の味であることを痛感致しました。宗匠は生前、「茶の湯の世界は、菓子でも懐石でも、どうすれば一番ベストかということを追求してゆく世界ですよ」とおっしゃっておられましたし、又「まぁ、茶の湯ということが分かってきたのは、60歳過ぎてからやなぁ」とも伺いました。
茶懐石は最初から汁も飯も酒も出て、実に理に叶った流れで、料理が供されます。
旬の材料を厳選して、素材の良さを損なわぬことが調理の根底で、長年茶懐石を勉強させていただき、祖父のもんもな京料理の世界も相通ずることを確信出来ました。茶懐石と会席料理は、趣旨・目的も異なりますし、当然スタイルも違いますが、いづれにしましても旬の魚貝類、鳥類、野菜類、豆腐、生麩、湯葉など相性の良い素材を組み合わせて、おもてなしの料理に昇華させてゆきます。茶の湯の美学の要であります「取り合せの妙」が、献立を考える折にも最も大切になって参りますことを実感しております。
幸い長男純一も表千家に入門させて頂き、東京での得難い料理修行の機会も与えていただき、現在四代目を継ぐべく、家業に励んでくれております。
|
| |
|
|