|
|
 |
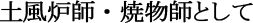 |

それが、江戸時代中期に至り、焼物師への道を歩み始めることになりました。昔は釜ごとに土風炉が作られていましたが、どのような種類の釜でも据えることのできる土風炉となり、6代覚々斎の頃になると土風炉の需要そのものが減ってきました。
さらに、10代了全のときに永樂家は天明の大火で全焼し、すべてを失ったのです。表千家のお家元をはじめ多くの方々の援助で家を再興した了全は、京焼の隆盛に機を見て、土風炉と同じ窯で焼ける香合や火入を造り始めます。これが、焼物師としての始まりでした。また、10代お家元吸江斎を通じ、紀州徳川家10代の治宝侯より「河濱支流」と「永樂」の印を拝領し、御庭焼に参入しました。続く11代保全は、金襴手など中国の焼物を日本人好みにアレンジし、12代和全は、仁清風の焼物を得意として製作を重ね、永樂家は焼物師の地位を確立しました。特に保全は、青磁などの唐物写しを得意とする青木木米とともに、京焼の名工として今に伝えられています。
とはいえ、実際には土風炉造りが主であり、了全も仕事の3分の2は土風炉造りであったと聞いていますし、実際、先代の即全まで土風炉を造っていました。実は、わたしは今日に至るまで、土風炉を造ったことはありません。しかし息子の陽一は、土風炉の製作を試みています。
|
| |
|
|