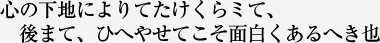 |
 |
ところで、珠光の言葉に似た考え方は、すでに連歌の世界で語られていました。室町時代の連歌師、心敬法師(1406-75)は正徹(しょうてつ 1381-1459)の和歌を評して、「唐の詩なとの面影まで添ひ、たけ高く冷え氷り侍る也」と言っています。つまり、正徹の和歌には唐の詩の雰囲気も感じられ、品格の高い、冷え枯れた境地にあったというのです。まさに漢詩のよさを十分に味わい尽くしたのち、冷え枯れた境地に至った和歌であったのでしょう。
このように、珠光の茶の湯の美意識には、連歌の影響が深く浸透していました。また珠光の周辺には柴屋軒宗長(さいおくけんそうちょう 1448-1532)のようなすぐれた連歌師がいて、珠光はそうした人たちと交流があったことも十分に考えられるところです。 |
 |
| |
 |
 |
 |
|
|