|
|

|
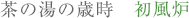
|
 |
端午の節句前後となれば暦では立夏を迎えます。立春より「八十八日」経(た)ち新茶の時期となります。茶人は炉より灰を上げ風炉へと替え夏のお茶の準備に入ります。畳は鍵畳より丸畳へ。その際畳の一枚が青く目立ちます。この時思い起こされるのが、如心斎の句です。『炉のあとは一畳青しほととぎす』。この句は芭蕉の句『花に寐む一畳あをき表かへ』を元にしたのではといわれています。堀内仙鶴を俳諧の師とした如心斎。芭蕉の句に何を想い詠んだのかはわかりません。また他にも、『茶話指月集』に古田織部の言葉として『樅のわか葉の出る比 風炉の茶湯よし』と残されています。
さて水も空気も清らかなこの時期、梁川紅蘭(やながわこうらん)の「思郷」や白居易(はっきょい)の「山泉煎茶有懐(山泉にて茶を煎て懐いあり」或いは于謙(うけん)の「偶題」が思い出されます。また新茶の時期となり茶摘みの歌が聞こえる気分の中、粽や柏餅を頬張り夏の訪れを迎えたいものです。
|
 |
|
|
 |
|
即中斎筆「青山緑水」
|
 |
|
|