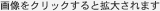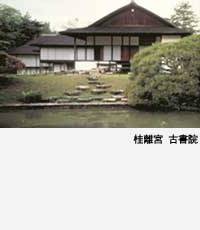|
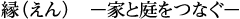
座敷が生まれ、屋内の生活が快適になりました。室内の襖や壁面には、風景や花鳥風月を描き、人々は自然界に思いを馳せました。また花を生けてみずみずしい美しさを観賞したりしました。そして座敷には、外に向かって開放された縁が設けられました。縁の上も深くさし出された屋根におおわれ、雨に濡れません。その先にさらに一段低く縁をつけます。これを濡縁と呼びます。座敷の床(ユカ)が、滑り出るように外へ外へと延びてゆきました。
縁という言葉は、「ふち」とも読み周囲を限る境界を意味します。同時に「御縁がありますね」と言うように、つながる意味も含まれています。縁は外から区切ると同時に、庭(自然)とつなぐ役割も果しているのです。座敷と一連なりの床(ユカ)が延びて、庭と触れ合い、結び合う、それは人と自然との融合を導く日本家屋の構造であり、縁がその主役を演じるのです。
|