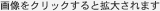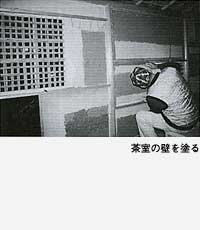|

茶室は一見、小さくて吹けば飛ぶような弱々しい建物です。しかし濃尾震災の時、名古屋の堀川沿いに建てられていた茶室が、滑り落ちてそのままの姿で舟のように浮いていたという話をききました。茶室自体は少しも壊れなかったのです。江戸時代の武家屋敷にあった地震の間は、数寄屋づくりの建物でした。
柱が細く、軽快に見える茶室は、実は見えない所に、工匠たちの技と労力が注入されているのです。
柱が細いので壁は薄くつくらなければなりません。そこで壁の中に貫を縦横に組むのです。水平の貫は柱を貫通する材で、それによって薄い壁を強化するのです。そして竹の小舞を細かく編みこみます。こうした頑固な骨組みが、茶室の壁の中に隠されているのです。茶室にとって大切な技術は、壁の中にあると言って過言ではないのです。
茶室で発達したこのような技術が、軽快さを求める数寄屋づくりに応用され、工匠たちのさまざまな創意工夫も展開されました。
|