|
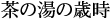
わが国では春夏秋冬の独特の景観を生み、季節に応ずる年中の諸行事を積み重ねて、時と場所と行事の積み重ねによる数多い伝承を「歳時」の名で伝えて今日に及んでいます。伝統の文化としての茶の湯がその意味を最も明らかに示すのは、「歳時」と共に歩む茶の湯をみる時であり、歳時と共に催される「茶事」の姿をみる時であります。
「茶事」は一年を通じ、四季にわたって催されます。
一般に茶の湯の世界は11月初旬、現在の暦での立冬(およそ7・8日ごろ)をもって新しい年のはじめとします。この日を迎えて茶室の「炉」をひらき、春に摘んだ新茶を葉茶の形で茶壷にたくわえたものを、壷の口封を切って使いはじめます。「口切」の時節というのがこれにて、新茶の使いはじめのこの時期を茶の湯の世界での正月とし、茶の庭の垣や樋の青竹を新しくしたり、茶室の畳を改め、障子を張替えるなどのことが行われます。この「口切」「開炉」の重なる時節の茶事は正午に客を案内して始められます。正午から約4時間にて懐石・濃茶・薄茶をもてなす「炉正午の茶事」が最も正式な茶事であり、茶事の基本の型をもっています。
「茶の正月」の茶事として、「口切」の茶事をはじめ、季節の移りに応じてどのような茶事があるかを略説しましょう。
「口切」の茶につづいて、冬の夕方から夜長を楽しむ「夜咄の茶」、厳冬の夜明けを楽しむ「暁の茶」、また5月初旬、立夏を迎えて炉から風炉に移り変る時期は、「初風炉」の茶事が行われます。夏の暑さきびしい頃は早朝の涼気を楽しむ「朝茶」が行われます。秋も深くなり10月には、昨年から使った茶の残りも少なく、又秋深い凋落の自然を味わう「名残の茶」の茶事が行われます。
|