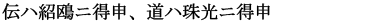 |
 |
利休は珠光をこよなく慕いました。たとえば利休が若き日におこなった茶の湯で「珠光茶碗」をよく用いています。これは高価な青磁ではなく、黄色がかった庶民的な青磁の茶碗と考えられています。また利休が円座肩衝の茶入を手に入れるかどうか考えあぐねていた時、それを投げ頭巾の茶入とともに何日か床に飾って眺めていたといいます。圜悟の墨跡は珠光が一休宗純から禅の印可証明(いんかしょうめい)として与えられたもので、利休もそれを尊重して自らの茶会でも用いました。利休は珠光の茶の道の伝統のうえに自らを位置づけていたといえるでしょう。
千家のわび茶の伝統は珠光にはじまり、紹鴎、利休へと伝えられてきたとする意識は、3代元伯宗旦のなかにも強く貫かれていました。「茶の湯の伝授は紹鴎から受け、道は珠光から得た」ということばは、利休の茶の教えとして、この話を書きとめた随流斎のことばであるようにも思えます。
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|