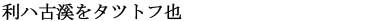 |
 |
ところで、古溪和尚が豊臣秀吉の意にそぐわず、西国へ配流処分となった時、利休居士は送別の茶会を開きました。しかもその茶会で利休居士が床に掛けたのは、秀吉から修復を頼まれて預かっていた有名な虚堂(きどう)の墨跡でした。利休居士があえてそれを掛けたのは、冬の晴れた寒い日の朝の送別の詩が書かれていて、古溪和尚への惜別の気持ちをこの墨跡の文言に託したからです。それはまさに、利休居士が大切にした人と人の心の交わりを象徴する茶の湯でした。
随流斎が書いた一文には、こうした歴史的な背景が凝縮されているように思えます。
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|