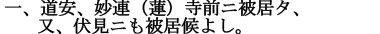 |
 |
また、道安は伏見にも居たと記されています。天正19年(1591) 2月28日に利休居士が自刃してからしばらくの間、道安の動向については確かなことがわかっていません。しかし、博多の豪商神谷宗湛の茶会記『宗湛日記』には、慶長2年(1597) 3月1日、道安が伏見でおこなった茶会に宗湛が招かれた記録があります。また、それから6年後、『松屋会記』の慶長8年(1603)10月12日条には、道安が堺で松屋久好を招いた茶会が記録されています。道安も秀吉から許されて再び茶堂にとりたてられ、秀吉の伏見城の近くに住んでいましたが、慶長3年に秀吉が没して道安は堺に帰ったのでしょう。
道安は堺にもどってから、慶長5年には大徳寺の春屋宗園(しゅんおくそうえん)より「眠翁(みんおう)」の道号を授けられました。さらに翌年には「茶の湯道歌」(表千家不審菴蔵)をしたためています。
道安は利休の堺の家屋敷を相続し、その地において利休居士の茶の湯を継承しました。
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|