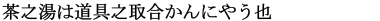 |
 |
しかし、江岑がこのように記したのは、初祖の利休以来、千家に伝えられてきた茶の湯のあり方であったと考えられます。利休の茶会記を見ると、ほとんど同じ道具で何回も続けて茶会をおこなっています。二代少庵、三代宗旦には、利休ほどまとまった茶会の記録はありませんが、おそらく利休のやり方を学んでいたと思われます。四代の江岑は、こうした茶会での道具組みのあり方を千家の茶のならい(教え)として、茶書に明文化したのでしょう。道具組みを替える時期を三つに区分したのは極端かもしれませんが、道具を十分に吟味して取合せることの大切さを強調しているのだと思われます。
江岑以後、ことに茶会記が豊富に残されている江戸時代中期の六代覚々斎、七代如心斎、そしてそれ以降は、ほぼ同じ道具組みで何ヶ月にもおよぶ一連の茶会が催されています。江岑が茶書に記したことばは、のちの千家の教えとして、時代に即しながら継承されていったことがわかります。
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|