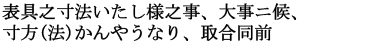 |
 |
江岑は表具の寸法を書き留めた寸法帳を何冊か残しています。そのなかには、たとえば利休が表具をした春浦宗熙の文(ふみ)の寸法が詳しく記載されています。本紙の大きさは縦8寸1分(24.5㎝)、横8寸5分(25.8㎝)とありますので、少し横長であったことがわかります。そして、この表具の「上」(「天」)が1尺3寸3分(40.3㎝)、「下」(「地」)が6寸8分(20.6㎝)。中廻しの上と下の部分はそれぞれ7寸(21.2㎝)、3寸5分(10.6㎝)、一文字の上と下の部分はそれぞれ1寸1分(3.3㎝)、8分(2.4㎝)とあります(これらは縦の幅の寸法です)。そして風帯の横幅は7分(2.1㎝)と記しています。
このように、江岑は主に利休をはじめ少庵、宗旦が表具をほどこした掛物の寸法を書きとめているのです。
江岑は、本紙の大きさとバランスのとれた表具をするため、利休をはじめとする先達のほどこした表具の寸法を手本にしたのでしょう。
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|